
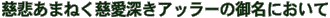
東京モスク
田澤拓也著
(一)
晴れわたった初夏の空の下で、異国の少年少女たちが手に手に緑の小旗を振っている。
昼下がりの強い日差しに、彼らの白い額と茶色い髪は汗ばむようだった。ときおり仰 ぎ見る頭上には、一本の尖塔がまるで天を突きさすように高くそびえ立っている。
昭和一三年五月一二日。東京市渋谷区代々木大山町の坂道の上に前年秋から建設がは じまっていた東京モスクは、この日、開堂式を迎えていた。
前年七月七日、北京郊外慶溝橋での一発の銃声に端を発した日中戦争は、もうすぐ一 年を経過しようとしていた。すでに前年二一月には日本軍は首都の南京を陥れている
。年が明けた一月には、さらに大陸奥地に首都を移した蒋介石政府に対し、時の近衛 文X[不明漢字]内閣(第一次)は「国民政府を相手にせず」との声明を発している。
しかし当初の事変不拡大方針とはうらはらに、日本軍は中国各地に追撃の手を緩めず 、徐州に進軍を続け、この日、厦門を完全に制圧しつつあった。一方、国内において
は四月に労務・物価。賃金。物資などあらゆる国民生活を政府の統制下に置こうとす る国家総動員法が公布されている。一二月には、この法律が全面的に発動されること
になる。東京モスク開堂式から二週間後の五月二七日にはロシアのバルチック艦隊を 潰滅させた日本海海戦から三三周年の海軍記念日を控え、全国各地で盛大な式典が予
定されていた。
軍靴の音が次第に高まり、日本が軍事色一色に塗りつぶされていこうとするなかで、 東京モスクは建設されたのである。すでに三年前、神戸の中山手通に日本で初めての
モスクが建設されていたが、東京での設立は首都圏に住んでいるムスリムたちの長年 の悲願であった。
B29による空襲や阪神大震災の激震にも耐えて、現在も神戸の坂道の中腹に立つ神戸 モスクは、昭和一〇年九月に設立された。日本有数の国際都市の神戸には、戦前から
多くのインド人貿易商などが住んでいた。当時まだインドはイギリスの植民地であり 、そのインドからムスリムの国であるパキスタンも分離独立していない。インド人の
彼らは大阪の繊維製品の輸出や、宗主国イギリスをはじめとするヨーロッパとの貿易 などで財を成していた。こうした富裕な人々のほか、ロシア革命で難民となって日本
に逃れたトルコ系の住民などで、当時、阪神地方には千名ちかいムスリムがいたとみ られる。
神戸モスクの建設に、とりわけ功績のあったのはフィローズディンとボチアという二 人のインド人貿易商である。モスク建設のために集められた総額約一二万円のうち、
フィローズディンは一人で六万六千円を寄付している。ムスリムの数が増えるにつれ て、各人の自宅などで礼拝をしていた彼らは自分たちのモスクを建てようと一〇年ち
かく計画を練り自らの力によってこのモスクを建設したのである。
その神戸モスク建設から三年がすぎていた。だが、東京モスク設立の経緯は、神戸モ スクの場合とは大きく異なっていた。
東京モスクの開堂式を報じる翌一三日付の『東京朝日新聞』の見出しは、「王子様も 防共の祈り回教の礼拝堂落成氏」とされている。
この日は回教始祖マホメットの千六百四十七年の生誕記念日、日本人の手で始めて出 来たこのマスヂト(筆者注・モスクの意)の落成を寿ぐため全世界四十数ヵ国からの
祝賀使節(中略)が来朝。これを迎えて在日回教徒四百名はその熱烈な団結の誓いに 「防共」の祈りを捧げるのだ。
開堂式に集まった約四百名の在日ムスリムの大半は、トルコ系の無国籍の難民たちだ った。首都圏に住む彼らにとって、東京にドーム(円屋根)とミナレット(尖塔)を
備えたモスクを建設することは、まさに大きな悲願だった。だが、わずか四百人ほど のこうした難民たちの力だけでは、都内に本格的なモスクが建設できるはずはなかっ
たのである。
式典が進むにつれて、東京モスク建設の真の主役たちの姿が次第に明らかになってい った。先の『東京朝日新聞』の記事はこうつつづいている。
午後二時東京トルコタタル文化協会会長ガリ・ダシキー僧侶が五階建円錐形の古典的 な塔に上り開会の合図、「オーオー」と叫んで「アザン」(筆者注・礼拝の呼びかけ
)の式を終れば直ちに頭巾満翁によって開扉、。続いてフーセン殿下を初め参会者一 同が静々と会堂に入り九十五歳のイブラヒム翁に依って礼拝、ヤングラジー氏によっ
て回教経典コーランが厳かに読み上げられ……(後略)
記念すべきイスラム寺院の開扉をしたのはムスリムの一人ではなく、頭巾満だったの である。さらに、この開堂式に参列していた異色の顔ぶれは頭巾ひとりではなかった
。モスクでの開堂式が終わったあと、午後二時半から参列者は外に出て庭に設けられ たテント張りの会場で祝賀式がはじまった。
かつて山岡光太郎をメッカに同行した在日ムスリム界の長老のイブラヒムが開会の挨 拶をしたあとで『君が代』が斉唱された。さらにつづいて満州国皇帝・溥儀の従弟の
溥洸の発声で「天皇陛下万歳」が唱えられた。そのすぐあとに、今度は「回教徒万歳 」の発声の音頭をとったのは陸軍大将の松井石板だった。前年暮れの南京攻略戦で中
支方面軍司令官として総指揮をとった松井は、敗戦後、東京裁判のA級戦犯として法 廷に引きだされ、南京大虐殺の責任者であるとされて絞首台に消えている。
いかに首都圏初とはいえ、一イスラム寺院の落成氏にイスラム教とは何の縁もゆかり もない軍部や右翼の大立者が顔をそろえて「天皇陛下万歳」と大声で唱えるさまを、
はるばる中東から訪れた招待客たちは、いったいどんな表情で見守っていたことだろう。
来賓たちからの祝辞がはじまった。
最初に、木戸幸一文部大臣の祝辞が代理として出席した政務次官の内ヶ崎作三郎によ って読み上げられた。木戸文相の祝辞は次のように結ばれていた。
「いまや東亜の黎明いたらんとして、民族協和の精神、日に高揚せんとするのとき、 諸子と我が国民との間に文化を媒介とする相互の理解と親善のいよいよ密ならんこと
を信ずるとともに、強き信仰の力によって言語風習の相違にもとづくあらゆる困難に 打ち克ち、相ともに人類福祉の増進に資するところあらんことを切望する次第であり
ます。」
つづく東京市長・小橋一太の祝辞には、さらにイスラム寺院の落成セレモニーには相 応しくない言葉がいくつもちりばめられて、日本の国策の影が露骨に投影されていた。
「いまや文化の進歩逐日顕著なるにかかわらず、国際関係ますます複雑をきわめ、帝 国はやむを得ず降魔の剣をとって事変の解決を図り、世界平和の確立に邁進しつつあ
るの秋、防共の強化、文化の擁護においてその精神を同じうする回教同憂の士の決起 を見るは欣快とするところなり。」
この二人の祝辞に対して、サウジアラビア国王の名代として列席していたワハバ駐英 公使の祝辞は、「東亜」や「防共」などといった言葉とは全く無縁で、はっきりと一
線を画していた。公使の祝辞はきわめてありきたりのものだったが、それだけに列席 しているムスリムたちの内心の違和感が、いっそうきわだってくるようだ。
「神は偉大なり、神は偉大なり……偉大なる神は正しき回教徒と真の信者の上にあり。
日本国民は急速なる発展をとげ、その行動において、またその組織力において、こと にその商工業において、その偉大性を世界に示された。私は、皆様方が皆様の前途に
横たわるすべての障壁を除去し、日本の人々がマホメットの真の精神を知るように努 力されんことを希望します。」
日本側の参列者とムスリム側の列席者と、その内心の落差はきわめて大きかったとい ってよい。各国からの祝賀使節の一行は、翌日から国会議事堂を訪れたり、陸軍の戦
闘演習や海軍の軍艦見学などをして、それぞれ属国していくことになる。
実は、この開堂式の日、それまで東京モスク設立の中心人物として東奔西走し、彼ら に招待状を発送していた四八歳の人物の姿が忽然として消えていた。この開堂式は主
役不在の式典だったのである。
その人物の名前はムハンマド・アブドルバイイ・クルバンアリー。彼は、この開堂式 前後の三日間、ひそかに警視庁に身柄を拘束されていたのである。
(二)
クルバンアリーを中心とするトルコ系難民たちの大半は、東京モスク開設から二〇年 ほど前、第一次大戦のさなかに起こったロシア革命をのがれて日本にたどり着いてい
た。革命に席巻されたロシアの大地から命からがら逃げてきたトルコ系ムスリムたち の歴史は悲惨だった。
モスクワとウラル山脈のちょうど中間にあるカザン。この一帯には、古くからロシア 人とムスリムのトルコ系タタール人とが混在して住んでいた。カザン市郊外の人口三千人のサラアシ村は住民のほぼ全てがタタール人だった。
このサラアシ村で生まれたテミムダル・モヒトの生年月日は「一九一九年五月一五日 」とされている。日本流にいえば大正八年の五月。パリでは第一次大戦の講和会議が
開かれていたころである。しかし、このモヒトの誕生日はのちになって決められたも ので、正確な日付はもう確かめようがない、ロシア革命の嵐のさなかに生まれたモヒ
トの誕生日を届けでたモスクも村役場も、その直後に焼失してしまったからである。
カザン市の南でボルガ河と合流するのがカマ河である。水量豊かな大河だが、冬の間 は凍結し、やがて春がくれば氷がとけて青い河が流れだす。その氷が割れて流れてい
くときにモヒトが生まれたと母親は記憶していた。「いつごろ?」と聞くと「五月ご ろ」という答え。それでは五月の真ん中にしようと、亡命したあとでモヒトの誕生日
は定められた。
カマ河のほとりのサラアシ村には三つのモスクがあった。そして四つめのモスクを建 設しようというときに革命の大波がこの片田舎の村にも到達した。村役場やモスクは
次々とロシア人による焼き打ちに遭い、共産主義にふさわしくない村の指導者やイン テリ層は大半が虐殺された。地主だったモヒト一家も、赤軍が通りすぎるまで隣村に
避難しようと生まれたばかりのモヒトを抱え、ほとんど着のみ着のまま同然で家を出 た。だが、その隣村もまたたくうちに蹂躙されて家族は流浪しながら東へ東へと難を
のがれる。
バイカル湖の近くの町に着いたとき、同行していた老齢の祖父は「もう私は逃げ切れ ないから、ここにのこる」と言って、伯父の家族とその町にとどまった。だがモヒト
の父はロシアにとどまろうとはしなかった。
「この神を信じない者たちの国にのこったのでは、子供たちがかわいそうだ。」
どうにかシベリア鉄道に乗ったときには、母がチフスに冒されて、両親と四人の子供 は凍てつくタイガに放りだされた。そうした危機を乗り越えながら二年がかりでよう
やくハルビンの街にたどり着いたのである。
かつて東清鉄道建設に従事したロシアの技術者や労働者が作ったといわれるハルビン の街にはモスクもあって、モヒト一家と同じ境遇の白系ロシア人やトルコ系難民たち
も多くいた。地主から一文なしの難民に転落した彼の一家は、さまざまな仕事に従事 しながらハルビンで一一年間を暮らした。
昭和七年、モヒト少年が一三歳のとき、一家はハルビンに別れを告げて東京にやって きた。その数年前に東京在住のトルコ人と結婚し、湯島で洋裁店を経営していた姉夫
婦をたよったのである。
一家が満州で暮らした時代はちょうど満州事変の勃発する前後だが、ようやく満州ま でのがれてきたトルコ系難民たちが、そこから対馬海峡をわたって日本内地に入国す
るのは容易ではなかった。日本での仕事のってはもとよりビザを取得するために当時 で一人当たり千五百円のお金が必要だったとモヒトは言う。
「千五百円のお金を見せなければ、日本政府に対する証明にならないのです。千五百 円といえば当時は家が一軒買えるほどでした。」
国籍のない難民たちは一〇円のお金にすら不自由している。五〇銭でも一円でも手元 にあれば有難いという人々にとっての千五百円である。その大金を都合して一人また
一人と日本に渡航できたのは、先に日本に着いて商売をはじめていた同郷ムスリムた ちの篤志が大きく貢献していた。日本でいくばくかの成功を収めて現金を手にした彼
らは、ハルビンのイスラム僧侶に千五百円ずつ送っては、次々に日本で働きたい人た ちを呼びよせたのである。千五百円の見せ金のほかに、服装をととのえる費用と、日
本までの片道の汽車賃と食事代も添えられていた。大金を託すのに一筆の借用書も取 らず、ただ「トルコ人。ムスリム」という信用だけが彼らの絆だったという。
かりに二人を招くだけでも三千円強の費用がかかるのだから、一度に一〇人も二〇人 も連れてくることはとてもできない。日本に着いた難民は、さっそくその恩人のもと
に千五百円を返しに出向いて仕事を紹介してもらう。当時、彼らが日本でできる商売 といえば、せいぜい洋服商や金物商、そして多くは問屋から仕入れたラシャの行商に
従事していた。
千五百円を返しにいけば、日本に招いてくれた先輩は、さっそく品物をわたして日本 語が不自由でも行商をうまくやるにはどうすればよいかとノウハウを教えてくれる。
その利益から少しずつ満州からの旅費やはじめに借りた事業資金を返していって、返 済が終わればようやく晴れて自由ということになる。モヒトは言う。
「そのお金がグルグル回っていた。それで私が日本に来たとき、もう全国で亡命トルコ人は三千人ぐらいいたというのです。」
小さな家に大勢で住んで、爪に火をともすように必死の思いで貯めたお金は、やがて 家族や仲間を呼びよせる元手となる。勤勉に働き、日本の当局ににらまれるような事
件は絶対に起こさない。誰かが病気になれば皆で面倒をみる。故国を捨てて、遠い異 郷の地で暮らす彼らのムスリムとしての団結心は強かった。
昭和の初めに東京近辺に住んでいたトルコ系の約四百人の人々の中心にいたクルバン アリーも、ロシア革命をのがれて日本に亡命してきたトルコ系バシキール人だった。
一八九〇年にウラル山脈の東のふもとのチェリャビンスク郊外の村で生まれた。すな わちモヒトより三〇歳ちかく年上になる。
チェリャビンスクはモヒトの故郷のカザンより東に七百キロほど離れているが、この 地に住むバシキール人たちも、やはり古くからのムスリムで、一四世紀以来、しばし
ばロシア人との間に衝突をくりかえしてきた。
クルバンアリーはイマームの家に生まれ、イスラム高等学校に学び、自らもイマーム の資格を得ていた。革命に直面し、ロシアの一地方民に甘んじていたバシキール人た
ちもまた反革命に決起した。反ソ連のチェコスロバキア軍やカザック軍と呼応しなが ら、クルバンアリーもタタール軍の一員として宗教を否定する赤軍に戦いを挑んだ。
戦闘は激烈だった。赤軍はイスラム教徒のおうさつ捕虜は鼻をそぎ耳をそいで容赦な くおう殺していった。
転戦のさなかにクルバンアリーはチェリャビンスク北方のエカテリンブルグで皇帝ニ コライ二世の一族が銃殺されたあとも目撃したという。
クルバンアリーらの部隊は、次第にオムスク、トムスク、イルクーツクとシベリア鉄 道沿いに東に撤退を余儀なくされる。ようやく約六百名の仲間とともにチタまでたど
り着いたとき、おりからシベリア出兵で同地に駐屯していた日本軍と出会って亡命を もとめたという。ロシア革命に乗じようとしたシベリア出兵で、日本軍は大正七年九
月にチタを占領し、九年八月に撤退するまで約二年間この地にとどまっていた。
このとき亡命した敗残タタール軍のある者は満州に職をもとめて定住し、ある者はト ルコやアメリカヘと散っていったが、やがて、このうち半数前後が日本にわたった。
クルバンアリーは大正一五年の六月に奉天(現瀋陽)で見合い結婚している。すでに 三〇代半ばになっていた。一〇歳年下の妻のウンム・グルスムは、カザンの南西約四
百キロにあるペンザで生まれたタタール人である。彼女の一家も、やはり革命をのが れて満州に亡命していた。結婚後しばらくは東京と満州を往復して暮らしていたクル
バンアリーだが、やがて東京で腰を落ち着ける。イマームの資格を持っていて宗教心 のあついクルバンアリーは、ほどなく東京に住むトルコ系難民たちのリーダー格とな
っていった。
イスラミックセンターパンフレットのページへ戻る
聖クルアーンのページへ戻る
ホームページへ戻る

